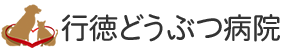ブログ
猫の自傷性脱毛について – 見逃しがちな痒みのサインについて獣医師が解説
2025.04.22
目次
愛猫の被毛が薄くなっていたりしませんでしょうか。
「そういえば最近、愛猫のお腹の毛が薄くなっている」
「愛猫が自分の毛をむしっているが大丈夫だろうか?」
といった不安をおもちではないでしょうか?
それは「自傷性脱毛」かもしれません。猫の自傷性脱毛は、疾患の重要なシグナルのひとつです。
今回は、猫の飼い主様に
- 自傷性脱毛とは
- 脱毛する原因
- どのような治療法があるか
について解説します。
猫の自傷性脱毛とは?
猫の自傷性脱毛とは、猫が自分自身で被毛を過剰に毛づくろいしたり、噛んだり、引き抜いたりすることで起こる脱毛のことです。
自傷性脱毛の見分け方
自傷性脱毛の特徴に、以下のようなものがあります。
- 毛が短く切れたようになっている。
- 局所的に、境界の明瞭な脱毛がある。
自傷性脱毛と通常の換毛期の違い
季節の変わり目には、猫は通常の換毛を行います。自然な脱毛(換毛期)であれば、全身の毛は均等に抜け、局所的に地肌が露出することはありません。
自傷性脱毛の主な原因
自傷性脱毛につながる過剰なグルーミングは、痒み、痛み、精神的ストレスによって引き起こされます。皮膚疾患だけでなく、関節の痛みや内臓の不調など全身的な問題が原因で起こるという点に注意が必要です。
主な原因は以下のようなものがあります。
- 皮膚病
- 痛みや違和感
- 精神的ストレス
- 腫瘍
皮膚病
皮膚病による痒みは、過剰なグルーミングを引き起こす代表的な原因です。
具体的にはノミやダニなどの寄生虫、食物や環境由来(ハウスダストや花粉など)によるアレルギー、アトピー性皮膚炎があります。
細菌やウイルス、糸状菌(カビの一種)などへの感染も痒みをもたらします。
痛みや違和感
体の痛みや不快感も過剰なグルーミングを引き起こします。痛みを引き起こす原因としては、関節炎や膀胱炎、肛門腺炎などがあります。
また、肛門嚢が溜まっている状態や膀胱炎で下腹部に違和感がある際にも、その部位を集中的に舐めることで自傷性脱毛が生じます。
精神的ストレス
猫は精神的なストレスからも過剰なグルーミング行動を示すことがあります。
猫にとってのストレスのきっかけになるものとしては、以下のようなものがあります。
- 家族構成の変化(新しい動物の迎え入れ、子供が生まれる)
- 引っ越しや部屋の模様替え
- 来客の増加
- 騒音
- 猫のトイレの変更(猫砂の種類、トイレの形状、位置など)
人間にとっては何気ない変化でも猫にとっては大きな変化であり、ストレスになりえるので注意が必要です。
腫瘍(がん)
猫の自傷性脱毛は、体内の腫瘍(がん)が原因で発生する場合もあります。肝臓や膵臓にがんがあることで、2次的な脱毛が見られることがあります。
また、肥満細胞腫やリンパ腫といった皮膚にも発生するがんは、初期段階では小さなしこりから始まることが多く、病変部が痒みを引き起こすため、猫が過剰に舐めることで脱毛が生じます。
脱毛部位と特徴
自傷性脱毛は、主に猫自身の口や舌が届く場所に発生します。
代表的な脱毛部位としては、以下のような場所です。
- 胴体(わき腹)
- お腹
- 太ももの内側
- 後ろ足の付け根
- お尻
原因疾患の診断
猫の自傷性脱毛は様々な原因が考えられるため、原因を特定するためには複数の検査が必要です。以下のような検査を組み合わせて総合的に判断します。
- 身体一般検査
- 皮膚検査
- 血液検査
- 尿検査
- 超音波検査
- レントゲン検査
身体一般検査
身体検査では、脱毛部位の状態から、皮膚の状態、リンパ節の腫れ、体温、体重などを確認します。
皮膚検査
皮膚検査では脱毛部位の皮膚や毛を検査し、細菌や真菌(カビ)、寄生虫の有無を確認します。より詳細な診断が必要な場合は、皮膚の一部を採取して病理検査を行うことがあります。
血液検査
血液検査は、脱毛の原因となる全身性疾患を診断するために重要です。炎症や感染の有無、内蔵機能の評価やホルモン疾患との関連を確認します。
尿検査
尿検査では、泌尿器系の問題や糖尿病など、脱毛に関連する可能性のある疾患を調べます。
画像検査
超音波検査では、内臓器官の異常を詳細に確認し、レントゲン検査では 骨格系の異常や関節炎の有無などを確認します。
自傷性脱毛の治療
猫の自傷性脱毛の治療は、原因に応じて適切なアプローチが必要です。
皮膚疾患の治療
皮膚疾患が原因の場合、それぞれの疾患に適した治療が行われます。
ノミやダニなどの寄生虫が原因であれば駆虫薬を使用し、細菌感染には抗生物質、真菌(カビ)感染には抗真菌薬による治療を行います。
アレルギー性皮膚炎の場合は、原因アレルゲンの除去に加え、抗炎症薬や免疫抑制療法、低アレルゲン食への変更などを組み合わせた治療を行います。
内臓疾患の治療
内臓疾患が原因の場合、その疾患に対する治療が必要です。
内分泌疾患の場合は、ホルモンの補充や調整剤が必要です。
膀胱炎や尿路結石などの泌尿器疾患では必要に応じて抗生剤や療法食での食餌療法を行います。
腫瘍性である場合には手術や薬による治療を行います。
ストレス関連の治療
心理的ストレスが原因の場合、ストレスの原因を取り除くことが治療につながります。猫が安心できる室内環境として、飼い主様とのふれあう時間を増やす、トイレ環境の改善、猫の探求心を刺激するような遊びの導入などが効果的です。
ストレスが原因の自傷性脱毛は、治療に時間を要するケースが多いため、治療期間中はエリザベスカラーや猫用の保護服で過剰なグルーミングを防止しましょう。
まとめ
猫の自傷性脱毛は、単なる美容上の問題ではなく、様々な健康問題のサインである可能性があります。また、原因は多岐にわたり、皮膚疾患から内臓の問題、さらには心理的ストレスまで幅広い要因が考えられます。
掻いている姿を見なくても脱毛があれば痒みを感じている可能性がありますので、当院までご相談下さい。
監修:行徳どうぶつ動物病院
アーカイブ
- 2026年2月 (4)
- 2026年1月 (7)
- 2025年12月 (10)
- 2025年11月 (8)
- 2025年10月 (4)
- 2025年8月 (1)
- 2025年6月 (2)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (6)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (4)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (5)
- 2022年11月 (4)
- 2021年11月 (1)
- 2021年9月 (1)
- 2021年3月 (4)