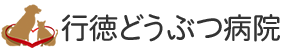ブログ
リクガメの冬支度
2025.10.31
院長ブログ

ついこの間まで夏だと思っていたのに、すっかり寒くなりましたね。すでにヒートテックが手放せない院長の名古です。それでも手がきんきんに冷えてやがって、妻に「生きてる?」と心配されます。秋、恋しいよ秋。どこへ行ってしまったの。
気温が下がってくると、リクガメたちの様子にも変化が現れます。夏のあいだは明るくなる前から餌皿の前で待機して飼い主に圧をかけていましたが、いまでは照明が点いて暖かくなってくるまで起きてきません。それ自体は自然な変化なので慌てる必要はないですが、そんな姿を見ると、そろそろ冬支度をしないとなあ、と思います。
やることはふたつ。寒さ対策と、乾燥対策です。
と言っても、うちは飼い主(私)がずぼらなのであらかじめオートメーションを施してあり、室温が24℃を下回ると勝手に暖房がつくようになっているので、それほどやることがあるわけではありません。だからヒートテックが手放せなくなっても、悠長にかまえているわけですね。科学の力ってすげー。こういう場所なので具体的な商品名を挙げるのは憚られますが、外出中でも温度や湿度がわかったり、出先からエアコンの操作ができたりするIoTデバイスは、動物飼育にとても役立つので採り入れ得です。常に誰かが家にいるという小泉政権以降なかなか確保が難しくなった環境ではない方は、使ってみるとよいと思います。常に誰かが家にいるとしても、機械に任せられるところは機械にまかせてしまったほうが楽ちんですしね。
で、我が家で行っているエアコン以外の寒さ対策は、カメたちのケージの下にパネルヒーターを敷くことです。うちにいるヨツユビリクガメは分布の北限が宗谷岬と同じくらいの緯度になるカメなので、実のところ、上に書いたエアコンの設定温度で保温は十分。エアコンが壊れない限り、個別に保温は必要ありません。ただ、勧めておきながらなんですがWi-Fiを介したエアコン管理はネットワークトラブルのリスクを抱えていて、Wi-Fiの不調により寒いのにエアコンが作動しない、ということが起こりえます。そんなときに備えて、ケージの中に一ヶ所、カメたちが体を温められる場所を設けておくのです。パネルヒーターなので空気を温める力はありませんが、直接暖をとりながら床材の中に潜っていれば、当座の寒さを凌ぐことができます。
なお、もっと暖かいところに棲んでいるカメを飼っていたり、小さな子ガメを飼っているならば、白熱電球や赤外線ヒーター(ケージの網蓋のうえに置くやつが売られていますね)も併用して、さらに温度を上げる必要があります。エアコンの設定温度を30℃にする方法もありますが、人間がつらいことと、電気代が天文学的な数字になることからお勧めしません。
乾燥対策のほうは、意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。ヨツユビリクガメは砂漠みたいなところに棲んでいて、乾燥系のリクガメ、湿気は苦手なんて言われていますから。でも、実はそこまで乾燥に強くはありません。乾燥がきつい時期は土に潜ってやりすごしていますからね。冬の日本の屋内の砂漠なみの湿度(加湿器をつけていないときの我が家の湿度は30%を切ります。サハラ砂漠のほうがまだ潤っていますね)ではなかなか厳しいので、対策が必要です。過度な乾燥は、呼吸器疾患、皮膚疾患、脱水による腎疾患、成長線の乾燥による甲羅の成長異常(ぼこつき)を招きます。
我が家の対策はシンプルに加湿器です。我が家にはひでりでスリップダメージを受ける人間(私)と慢性腎臓病の猫がいるので、カメがいようがいまいが加湿器は必須(カメの話だと思って油断していたそこのあなた、いまちょっと大事なこと言いましたよ。乾燥した空気は体から水分を奪う力が強いので、ただでさえ脱水しやすい腎不全の猫をよりカラカラにしてしまいます。乾燥、ダメ、絶対)。どうせ部屋ごと加湿しているので、それがついでにカメの乾燥対策にもなっています。
加湿力だけで言ったらスチームタイプがいいのですが、猫が乗ると危ないし、電力消費量がえげつないので使いにくく(妻が別の部屋で作業をするときに小型のスチーム式加湿器を使うことがありますが、加湿器と電気ケトルと電子レンジを同時に使ったらブレーカーが落ちました。リビングで24時間使用は無理そう)、やむなく気化式のものを使っています。本体が生産終了していて、替えのフィルターがビックカメラの通販でしか手に入らないので、毎年ひやひやしながら冬を迎えます。セールだからと知らないメーカーの製品にとびつくのは良くない。みなさんは高くても大手のやつを買うことをお勧めします。
なお、これだけでは幼いリクガメにはつらいことがあるので、さらに素焼きのシェルターを置いたり、霧吹きしたりして、湿度の高い場所、時間を作ることで乾燥を防いでいきます。
爬虫類が体調を崩す原因の第一は不適切な温度、第二は不適切な水環境(飲水・空気中の湿度を含む)です。冬場はどちらもが望ましい条件から外れてしまうので、こうして対策しなければいけません。
まあ、さっきも書いたようにヨツユビリクガメは冬のある地域(生息地によっては気温がマイナス50℃とかになる)に生息するカメなので、冬眠させてしまえば冬の管理はかえって楽です。ただ、いまの住まいではカメを安全に冬眠させられる場所がないので、冬眠せずに冬を越せるように、こんな準備をしています。
爬虫類飼育は冬が鬼門。みなさんも、大事などうぶつが体調を崩さないように、しっかり冬支度をしてあげてくださいね。
アーカイブ
- 2025年12月 (10)
- 2025年11月 (8)
- 2025年10月 (4)
- 2025年8月 (1)
- 2025年6月 (2)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (6)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (4)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (5)
- 2022年11月 (4)
- 2021年11月 (1)
- 2021年9月 (1)
- 2021年3月 (4)