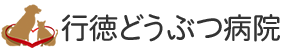ブログ
【獣医師監修】犬が足を舐める理由と指間炎の治し方|自宅ケアと病院治療を完全解説
2025.11.10
目次
「愛犬が足の指の間をずっと舐めていて、赤く腫れてきた」
「舐めるのをやめさせたいけど、どうすればいい?」
当院の皮膚科外来では、こうした相談が全体の約30%を占めます。犬が足を執拗に舐め続ける行動は単なる癖ではなく、指間炎(しかんえん)という炎症のサインです。
この記事では、指間炎の原因から治療法、ご自宅でできる予防ケアまで、飼い主様が本当に知るべき情報を凝縮してお伝えします。

【緊急度別】今すぐ病院に行くべき症状チェック
まず、愛犬の足の状態を確認してください。以下の症状に当てはまる場合、早急な受診が必要です。
🚨 今すぐ〜24時間以内の受診が必要
- 足を地面につけられない、引きずって歩く
- 患部から血や膿が出ている
- 患部が熱を持ち、赤く腫れ上がっている
- 食欲がない、元気がない
- 夜通し舐め続けて眠れない
- 何か刺さっているように見える(異物混入の可能性)
- 複数の足の指間が同時に腫れている
⚠️ 2〜3日以内の受診を推奨
- 指の間が赤くなってきた
- 舐める頻度が日に日に増えている
- 患部から独特の臭いがする
- 患部が湿ってべたついている
💡 様子見+予防ケアでOK
- 時々足を舐めるが、すぐやめる
- 目立った赤みや腫れはない
- 食欲も元気もいつも通り
判断基準: 10分以上舐め続ける状態が3日以上続いたら受診のタイミングです。
💬 今すぐ相談したい方へ
LINEで無料相談受付中
「うちの子の症状、病院に行くべき?」「応急処置の方法は?」など、気軽にご相談ください。
指間炎とは?症状と発症メカニズム
指間炎の定義
指間炎とは、犬の足の指と指の間(指間部)に起こる炎症の総称です。この部位は湿気がこもりやすく、細菌や真菌(カビ)が繁殖しやすい環境にあります。
こんな症状が見られたら要注意
- 指の間の皮膚が赤く腫れている
- 毛が抜けて地肌が見える
- 患部がじめじめと湿っている
- 独特の臭い(脂っぽい、納豆のような臭い)
- 血や膿が出ている
- 患部を執拗に舐める、噛む
- 痛みで歩き方がぎこちない
重要: 指間炎は一度発症すると慢性化しやすく、再発率が高い疾患です。
指間炎の主な原因
指間炎は単一の原因ではなく、複数の要因が関与します。
1. アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎は、皮膚のバリア機能異常と遺伝的素因が主な原因です。アレルギー反応とは異なるメカニズムで発症します。
アトピー体質の犬は、皮膚が乾燥しやすく外部刺激に弱いため、指間炎を併発しやすい傾向にあります。足の指間だけでなく、脇の下、お腹、内股、関節の曲がる部分などにも赤みや痒みが見られることが多いです。
2. アレルギー反応
特定のアレルゲン(原因物質)に対する免疫反応として指間炎が生じることがあります。
- 食物アレルギー: 特定のタンパク質(牛肉、鶏肉、小麦、大豆など)に対する反応
- 環境アレルギー: 花粉、ハウスダスト、ダニ、カビなどに対する反応
- 接触アレルギー: 草花、洗剤、シャンプーなどに直接触れることで起こる反応
3. 細菌感染(膿皮症)
黄色ブドウ球菌などの常在菌が、皮膚バリア機能の低下により異常増殖。湿った環境が続くと感染が進行し、膿を伴う膿皮症に発展します。
3. マラセチア皮膚炎
マラセチアは犬の皮膚に常在する酵母様真菌です。脂質バランスの崩れや免疫力低下で異常増殖し、患部は赤く腫れ、べたつき、独特の脂っぽい臭いを発します。
4. 異物の混入
散歩中に以下が刺さることがあります:
- イネ科植物の芒(のぎ):先端が鋭く、逆向きのとげで皮膚内を進む
- 小石、ガラス片、木片
5. その他(肥満、ホルモン異常、腫瘍)
肥満犬は足指への負担が増加し、指間の摩擦や圧迫で炎症が起きやすくなります。
舐めれば舐めるほど悪化する「悪循環」
指間炎治療の最大の課題が舐める行為による悪循環です。
悪循環のメカニズム
痒み・痛み
↓
舐める
↓
患部が湿る(唾液)
↓
細菌・マラセチアが増殖
↓
炎症悪化
↓
痒み・痛みが増す
↓
さらに舐める → 繰り返し
長期化すると、痒みがなくても「舐める」が習慣化し、行動性の問題に発展します。この悪循環を断つことが治療の最優先事項です。
【重要】絶対にやってはいけない4つのNG行為
❌ 1. 人間用の薬を使用
オロナイン、マキロンなどは犬には危険。舐めると中毒を起こす成分が含まれています。
❌ 2. 異物を無理に引き抜く
深く刺さったり、折れて体内に残る危険があります。
❌ 3. 放置する
「自然に治る」は幻想。悪循環が進行し慢性化します。
❌ 4. 熱いお湯で洗う
炎症を悪化させます。洗う場合はぬるま湯で。
⚠️ 自己判断での対処が不安な方へ
「今の状態で様子を見ていいの?」「応急処置は合ってる?」など、少しでも不安があればLINEでご相談ください。
動物病院での治療法(標準プロトコル)
1. 原因別の薬物療法
- 細菌感染: 抗菌薬(内服・外用)
- 真菌感染: 抗真菌薬
- アトピー性皮膚炎: 痒み止め(アポキル、サイトポイントなど)、保湿剤、皮膚バリア機能改善薬
- アレルギー反応: 抗ヒスタミン薬、ステロイド(重症例)、アレルゲン回避
- 外傷: 洗浄・消毒・鎮痛剤
2. 薬浴・足浴療法
抗菌・抗真菌シャンプーで週2-3回の薬浴を実施。クロルヘキシジンやミコナゾール配合シャンプーが一般的です。
重要: シャンプー後は完全に乾燥させることが必須。湿ったままでは逆効果です。
3. 足裏・指間の毛のカット
通気性改善と薬剤浸透を高めるため、余分な被毛をカット。特にトイプードル、シーズー、マルチーズなど長毛種で重要です。
4. 舐めさせない対策(最重要)
- エリザベスカラー: プラスチック製、布製、ドーナツ型など
- 保護ブーツ・靴下: 患部の直接保護
自宅でできる5つの予防策
1. 散歩後の足のケア(最重要)
必ず実施: 散歩後は濡れタオルで拭くか、水で洗い流す。その後、乾いたタオルで水分を完全に拭き取る。
工夫: 玄関に「足拭きセット」(濡れタオル・乾いたタオル・足拭きマット)を常備。
2. 定期的な毛のトリミング
月1〜2回、足裏・指間の毛をカット。湿気予防と汚れ防止に効果的。
3. アレルギー管理
- 食物アレルギー: 療法食の継続
- 環境アレルギー: こまめな掃除、定期的なブラッシング
食物アレルギーが原因の指間炎の場合、適切な療法食の選択が治療の鍵となります。
詳しくは関連記事をご覧ください:
👉 どうぶつの皮膚疾患に効果的な療法食の種類と選び方
4. 散歩の工夫
時間帯: 真夏は早朝・夕方以降。日中の熱いアスファルトは火傷の原因に。
コース選び: 草むらや異物の多い場所を避け、舗装された道を選ぶ。
5. 毎日の足チェック習慣
推奨タイミング: テレビを見ながら、ソファでくつろぎながらのスキンシップタイム。肉球を優しく開いて指間を確認。1日1回、15秒でOK。
チェック項目:
- 赤み・腫れ
- 脱毛
- 臭い
- 湿り気
指間炎になりやすい犬種
以下の犬種は特に注意が必要です:
- トイプードル
- シーズー
- マルチーズ
- ゴールデンレトリバー
- ラブラドールレトリバー
- フレンチブルドッグ
- 柴犬
これらの犬種は、足裏の毛が多い、皮膚が敏感、アレルギー体質などの特徴があります。
まとめ:早期発見と適切なケアが鍵
指間炎は正しい知識と対応で改善できる疾患です。
重要ポイント:
- 放置すると慢性化し、治療が長期化
- 「舐めさせない工夫」が治療の核心
- 原因は多様で、自己判断は危険
- 毎日の足チェックと散歩後ケアが最強の予防策
- 緊急度チェックで受診タイミングを判断
どうぶつ病院47グループのデータでは、早期発見・早期治療を行った場合、95%以上が2週間以内に著明な改善を示しています。
今すぐできる3つのアクション
1. 愛犬の足を今すぐチェック
指の間に赤み・腫れ・臭いがないか確認しましょう。
2. 少しでも不安があればLINEで相談
「病院に行くべき?」と迷ったら、まずはLINEでご相談ください。
経験豊富な獣医師が、症状を伺った上で適切なアドバイスをいたします。
👉 今すぐLINEで相談する
※相談無料・24時間受付
3. 予防ケアを今日から習慣化
散歩後の足拭き、定期的な毛のカットを生活に取り入れましょう。
「こんなことで相談してもいいの?」という遠慮は不要です。
少しでも気になることがあれば、お気軽にご連絡ください。
愛犬の健康を、一緒に守っていきましょう。
📚 あわせて読みたい関連記事
指間炎の根本原因がアレルギーの場合、食事の見直しが効果的です。
皮膚トラブルを繰り返すどうぶつには、体の内側からのケアも重要です。療法食の選び方を詳しく解説しています。
監修: 名古孟大 獣医師(行徳どうぶつ病院 院長)
最終更新: 2025年11月
アーカイブ
- 2026年2月 (4)
- 2026年1月 (7)
- 2025年12月 (10)
- 2025年11月 (8)
- 2025年10月 (4)
- 2025年8月 (1)
- 2025年6月 (2)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (6)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (4)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (5)
- 2022年11月 (4)
- 2021年11月 (1)
- 2021年9月 (1)
- 2021年3月 (4)