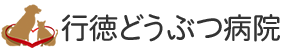ブログ
犬の二次性中耳炎について|外耳炎からの波及と基礎疾患の重要性について獣医師が解説
2025.04.08
愛犬が耳のトラブルを抱えた経験はありませんでしょうか?
「愛犬がしきりに耳を掻いたり、頭を振っているけれど大丈夫だろうか?」
「愛犬の耳から不快な臭いがする」
「動物病院で耳の治療を受けているが、中々治らない」
といった不安をおもちではないでしょうか。
これらは外耳炎の一般的な症状ですが、適切な治療を行わないと、さらに奥にある中耳まで炎症が進行してしまうことがあります。外耳炎や中耳炎の多くは単なる局所的な問題ではなく、アトピー性皮膚炎や食物アレルギー、脂漏性皮膚炎などの基礎疾患の一部として現れることが多いです。
今回は、犬の飼い主様に
- 外耳炎から中耳炎への波及メカニズム
- 原因となる基礎疾患
- どのような治療法があるか
について解説します。
犬の耳の構造
病気の解説に入る前に、犬の耳の構造について整理しておきましょう。
犬の耳は大きく分けて外耳、中耳、内耳の3つの部分から構成されています。
外耳
外耳は目に見える耳介(じかい)と、外耳道(がいじどう)からなります。
犬の外耳道は、人間と違ってL字に曲がっており、長さも約5〜10cmと長いです。構造上、外耳道の中の湿度が高く、細菌や酵母が繁殖しやすい環境となっています。
中耳
外耳道の奥には音波の振動を受け取る鼓膜があり、その内側に中耳があります。鼓膜のすぐ内側は、骨で囲まれた鼓室(こしつ)と呼ばれる空間です。ここは耳小骨とよばれる小さな骨があり、音の振動を内耳に伝えています。鼓室からは耳管と呼ばれる細い管が咽頭まで伸びていて、鼓室内の気圧を調整しています。
内耳
中耳のさらに奥には内耳があります。耳小骨から音の振動を受け取り、聴覚をつかさどる神経に伝える蝸牛、平衡感覚をつかさどる前庭、加速度を感知する半規管からなります。
中耳炎とは
中耳炎とは、読んで字の如く中耳に炎症が起きる疾患です。犬の中耳炎は人間と異なり、特有の症状が出づらく、外耳炎と見分けがつきにくいことがあります。
中耳炎を放置すると、さらに内耳にまで炎症が広がり、平衡感覚の異常や難聴、顔面神経麻痺などの深刻な合併症を引き起こす可能性があります。
二次性中耳炎
犬の中耳炎は、原発性のものと、外耳炎が悪化し、中耳まで炎症が波及することによって起こる二次性のものに分けられます。多くの場合は二次性です。外耳炎を繰り返している、または長引いている場合は、中耳炎につながる可能性が高いので注意が必要です。
外耳炎の原因
外耳炎の原因には以下のようなものがあります。
主因
主因は外耳炎発症の基礎となる因子です。代表的な例としては以下のようなものがあります。
- アトピー性皮膚炎
- 食物アレルギー
- 脂漏性皮膚炎
- 外部寄生虫
- 自己免疫疾患
アトピー性皮膚炎や食物アレルギー、脂漏性皮膚炎といった皮膚炎は、皮膚と共に、耳にもの症状が出ます。
耳ヒゼンダニというダニの仲間が外耳道に寄生すると、ダニに対するアレルギー反応で外耳炎が起こります。これはとくに幼犬に多くみられます。
素因
素因とは、外耳炎を発症しやすくさせる因子のことです。気候や異物、といった外的なものと、脂漏体質や外耳道の腫瘍といった内的なものに分けられます。
外的な因子として注意すべきは耳掃除です。頻繁な耳掃除や不適切な方法での耳掃除は、耳道を傷つけ、炎症につながることがあります。掃除をしているつもりで耳垢を耳道の奥に押し込んでしまい、外耳炎につながることもあります。
内的な因子としてもっとも多いのは、垂れ耳や耳道が狭いといった、犬種特有の耳の形状です。こういった形状の耳は湿気や熱がこもりやすく、耳垢も排出されにくく、炎症のリスクを高めます。特にコッカー・スパニエル、プードル、ラブラドール・レトリバーなどの犬種は注意が必要です。
持続・悪化因子
持続・悪化因子は外耳炎を悪化させ、長引かせる因子で、以下のようなものがあります。
- 細菌などの二次感染
- 炎症による外耳・中耳の構造変化
- 治療のために使用した薬剤に起因する薬疹
外耳炎の症状
もっともよく見られる症状は耳の痒みです。耳の痒みは、以下のような行動として表れます。
- 後ろ足で耳を掻く
- 床に耳をこすりつける
- 耳を振る
炎症が強くなり、痛みが出てくると、耳を触られたときにぎゃんと鳴いたり、触られるのを嫌がるようになります。
耳の外見的な変化としては以下のようなものが見られます。
- 耳の臭いがきつくなる
- 耳が赤くなる
- 耳垢が増える
- フケが目立つ
- 耳周囲の毛が脱毛する
犬の二次性中耳炎の治療法
犬の外耳炎や中耳炎の治療は、単に耳の局所的な処置だけでなく、原因に対する治療と管理が重要です。
耳の洗浄
専用の洗浄液を用いて耳道内にある耳垢を取り除きます。耳垢や炎症産物を取り除き、薬剤を浸透しやすくするためです。
長い間炎症が起こっている耳では一度耳洗浄しても、またすぐに新しい耳垢が分泌されやすい環境となっています。そのため、薬を使って外耳炎をケアしつつ、耳垢が分泌されなくなるまで洗浄を繰り返す必要があります。
犬の耳はとてもデリケートです。とくに鼓膜が傷つき、中耳炎まで波及している場合は注意深く洗浄する必要があります。
点耳薬・内服薬
外耳炎の治療は点耳薬による外用療法が基本となります。
点耳薬には、ステロイドだけが含まれたもの、抗菌薬や抗真菌薬が合わさっているものなどいくつか種類があり、作用時間も1日単位のものから1週間ないし1ヶ月効果が持続するものまでもあります。これらを状態によって使い分けていきます。
耳の炎症が強く、耳道が狭くなっている場合、痛みを伴いやすく、洗浄や点耳が難しい場合は、内服薬で痛みや炎症を和らげてから耳洗浄・点耳を行います。
外科治療
前述の治療ではコントロールできない場合は耳道を切除する外科手術が必要です。耳道が狭すぎる場合や、骨のように固くなってしまっている場合が該当します。耳道内に腫瘤があることで耳道が塞がれている場合も手術を行うことがあります。
基礎疾患の治療
耳道のケアと並行して、基礎疾患の治療を行います。
- 寄生虫に対する駆虫剤
- 内分泌疾患に対するホルモン調整剤
- 食物アレルギーに対する食事(アレルギーの原因となる食材を含まない特別に調製された食事)
といったそれぞれの基礎疾患に対するアプローチが挙げられます。
中耳炎は治るのか
中耳炎は、適切な治療を行えば改善します。しかし長期化した中耳炎や腫瘍やポリープがある場合は、再発を繰り返すこともあるため注意が必要です。
まとめ
犬の中耳炎は外耳炎の延長で生じるパターンが多いです。外耳炎のケアとその背景にある基礎疾患をきちんとコントロールすることで、愛犬の耳を良い状態に保てます。特にこれから暑い季節は湿度が高くなり、犬の外耳炎・中耳炎が起きやすい時期です。耳の変化に気づいた時は早めに当院までご相談下さい。
監修:行徳どうぶつ病院
アーカイブ
- 2025年12月 (10)
- 2025年11月 (8)
- 2025年10月 (4)
- 2025年8月 (1)
- 2025年6月 (2)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (6)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (4)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (5)
- 2022年11月 (4)
- 2021年11月 (1)
- 2021年9月 (1)
- 2021年3月 (4)