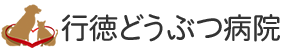ブログ
犬のフケが出るのは異常?様々な原因疾患と適切な治療法を獣医師が解説
2025.04.15
目次
愛犬の体にフケが出ているのに気づいたことはありませんか?
「最近、フケが目立つようになった」
「ブラッシングすると白い粉のようなものが舞う
「愛犬のフケは、乾燥からくるものなの?」
などの症状や疑問をお持ちの飼い主さんも多いのではないでしょうか。
犬のフケは、さまざまな皮膚疾患のサインである可能性があります。同じ「フケが出る」という症状でも、原因となる疾患によって治療法が大きく異なるため、適切な診断と治療が重要です。
今回は、犬の飼い主様に
- フケの正体
- フケの原因
- フケの対策
について解説します。
ぜひ、最後までお読みいただき、愛犬の皮膚トラブルの早期発見にお役立てください。
犬のフケの正体
犬の皮膚は、約3週間のサイクルで生まれ変わります。これを「ターンオーバー(新陳代謝)」といいます。
このターンオーバーの過程で、古くなった皮膚の角質細胞が剥がれ落ちたものが「フケ」です。正常ならば、このフケは目に見えないほど少量ずつ剥がれ落ちます。
しかし、何らかの原因でターンオーバーが乱れると、フケが過剰に発生し、白い粉状になったり、カサカサとした膜状になったりして、目立つようになります。
犬のフケが出る原因疾患
犬のフケには様々な原因があります。
乾燥
空気が乾燥すると、皮膚の水分が失われてフケが増えます。特に冬場や空調の効いた室内では注意が必要です。乾燥が原因のフケは、皮膚に細かな亀裂や線(ひび割れ)が入り、表面が薄く剥がれかけているように見えるのが特徴です。
不適切なスキンケア
愛犬に使っているシャンプーや皮膚ケア製品が、実はフケの原因になっていることがあります。
例えば夏場に汗をかくだろうと考えて脱脂力の強いシャンプーを使用すると、必要な皮脂や角質まで落としてしまい、皮膚の乾燥を招き、フケが増えることがあります。他にも、シャンプーの頻度が多すぎる場合や、すすぎ不足によるシャンプー成分の残留もフケの原因となります。
犬の皮膚は人間よりも薄く敏感なため、不適切なスキンケアはフケだけでなく、かゆみや炎症など他の皮膚トラブルにつながることもあります。
皮膚感染症
細菌やカビ、寄生虫による感染によってフケが発生します。感染によって皮膚に炎症が起こると、皮膚のターンオーバーが乱れてフケが増加します。
細菌感染(膿皮症)
膿皮症は、犬の皮膚にいる常在菌が何らかの原因により異常増殖することで引き起こされる皮膚トラブルです。特に皮膚の折り目部分や湿気の多い部位に発生しやすい傾向があります。
赤い発疹や、時には膿を伴い、黄色っぽいフケが出ます。
真菌感染(皮膚糸状菌症)
皮膚糸状菌症は、カビの1種によって起こる感染症です。円形の脱毛斑と共に白っぽいフケが見られます。人にも感染するため注意が必要です。
寄生虫感染(ツメダニ、疥癬など)
ツメダニや疥癬などの寄生虫感染では、強い痒みと共にフケが発生します。犬が頻繁に同じ場所を掻くため、皮膚から出血が認められることもあります。特に耳の縁や肘、膝などに集中して症状が現れることが多いです。
脂漏症
脂漏症は犬の皮膚の脂分泌が過剰になり、皮脂の多い黄色や黒色のフケが出る皮膚疾患です。特に背中や尾の付け根など、脂腺の多い部位に発生しやすく、独特の脂っぽい臭いを伴うことが多いです。脂漏症は皮膚の問題として単独で発生することもありますが、アレルギーや内分泌疾患などの他の皮膚病と併発することもあります。
内分泌疾患
中高齢の犬に多く発症する内分泌疾患も、フケが増える要因の1つです。ホルモンバランスが乱れることで皮膚のターンオーバーが正常に機能しなくなるためです。
代表的な疾患は甲状腺機能低下症や副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)が挙げられます。内分泌疾患によるフケは通常の皮膚ケアでは改善しにくく、中高齢犬で突然フケが増えた場合は注意が必要です。
犬のフケ対策と治療法
フケの原因によって適切な治療法は異なります。それぞれの原因疾患に対する効果的な対策と治療法をご紹介します。フケが長期間続く場合や、かゆみや赤みを伴う場合は、早めに動物病院を受診しましょう。
乾燥の場合
乾燥が原因の犬のフケには、皮膚の保湿と環境調整が重要です。
シャンプーをすると皮膚が乾燥するので、湿成分が配合された犬用シャンプーを選び、頻度も月1〜2回程度にとどめましょう。シャンプー後は保湿ローションで皮膚を乾燥から保護すると効果的です。
室内環境は湿度50〜60%を目安にしましょう。特に乾燥しやすい季節は加湿器の使用が必須です。
不適切なスキンケアの場合
スキンケアが原因のフケを改善するには、ケア方法の見直しが必要です。
シャンプー後にフケが増えるようであれば、シャンプーの種類や頻度の見直しが必要です。また、すすぎ不足は痒みやフケの原因になることから、シャンプー後は十分にすすぎましょう。
ブラッシング時に使用する道具によっては、皮膚を傷つけ、フケにつながってしまうことがありますブラッシングには先の尖ったスリッカーではなく、毛のブラシや先の丸いコームを使いましょう。
皮膚感染症の場合
感染症によるフケには、原因となる病原体の種類に応じた治療が必要です。
細菌感染(膿皮症)
膿皮症には殺菌作用のある薬用シャンプーを用いた外用療法を行います。毛穴や皮膚の深部まで感染している場合は、抗菌薬の内服を行うこともあります。
真菌感染(皮膚糸状菌症)
皮膚糸状菌症には抗真菌薬の内服を行います。
皮膚糸状菌は毛に感染するため、毛を短くカットしたり、抗真菌作用のあるシャンプーで洗浄したりするすることが治療の補助になります。
人や同居動物にも感染する可能性があるため、治療中の犬との接触は避け、手洗いを徹底しましょう。
寄生虫感染(ツメダニ、疥癬など)
ツメダニや疥癬など寄生虫が原因の場合は、まずは駆虫剤を投薬します。また、物理的に寄生虫や汚れを落とすためにシャンプーを実施します。
寝具やカーペットなど犬の生活環境の清掃と消毒も重要です。
脂漏症の場合
脂漏症の治療は過剰な皮脂分泌のコントロールが中心です。
治療には界面活性剤配合のシャンプーや保湿剤を使用し、過剰な皮脂を抑えます。
併発する内分泌疾患やアレルギーがある場合はその治療も合わせて実施します。
もともと皮脂の多い脂漏性犬種では、空調によって高温多湿な環境を緩和してあげる必要があります。
内分泌疾患の場合
内分泌疾患(甲状腺機能低下症やクッシング症候群など)によるフケは、基礎疾患の治療が必要です。甲状腺ホルモンの補充や副腎皮質ホルモンの合成を抑制する薬を使用します。
まとめ
犬のフケは単なる見た目の問題ではなく、様々な皮膚疾患のサインかもしれません。同じフケという症状でも、乾燥による軽度のものから、寄生虫感染や内分泌疾患まで、その原因は多岐にわたります。
多すぎるフケは、なんらかの皮膚トラブルを示唆するものですから、動物病院で診察を受けることをおすすめします。
監修:行徳どうぶつ病院
アーカイブ
- 2026年2月 (4)
- 2026年1月 (7)
- 2025年12月 (10)
- 2025年11月 (8)
- 2025年10月 (4)
- 2025年8月 (1)
- 2025年6月 (2)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (6)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (4)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (5)
- 2022年11月 (4)
- 2021年11月 (1)
- 2021年9月 (1)
- 2021年3月 (4)