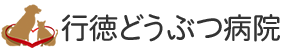ブログ
健康診断のすすめ
2025.08.01
院長ブログ
大腸内視鏡を受けた話
みなさんは、大腸内視鏡検査を受けたことがありますか。私はあります。去年の春から初夏にかけて、合計2回、あの暴力的な管に大腸を貫かれるはめになりました。
きっかけは、会社で受けた健康診断で、便潜血が認められたことです。精密検査を勧められ、健診を受けた病院は家から遠かったので近所の病院に相談したところ、紹介状を書くので大きい病院で大腸内視鏡の検査を受けなさいと言われました。
大腸内視鏡検査、これは地獄のような検査でした。前日から食事制限、夜からは絶食。夕方6時から食事がとれなくなるので、仕事が終わった時にはもうごはんが食べられない。実質24時間以上の絶食を強いられます。そのうえでまる1日病院に缶詰め、朝から下剤をがぶがぶと飲まされ数分ごとにトイレにGO。もう下剤以外出てこないという状態になったら検査待ちの待機列に組み入れられ、順番が来たらお尻丸出しで肛門から管を突っ込まれる。内視鏡が腸の中を通っていくときには、まるでチェストバスターが体内を這いまわっているような異物感、圧迫感を覚えます。空腹感に苛まれるわ時間はとられるわ辱めを受けるわお腹は気持ち悪いわと、検査における「嫌ポイント」を全部乗せにしたような検査でした。
しかも悪いことに、その検査では大腸ポリープが見つかったのです。肉眼所見は悪いもんじゃないが、とった方がいいとお医者様は言いました。合併症への準備が今日はないから、日を改めてやることになるけど、と。
ん? するってーとなんですかい? 私はこの苦行を、もう1回するってことですかい?
というわけで、1ヶ月ほどのインターバルをおいてもう1度、私は大腸内視鏡を突っ込まれ、ポリープの切除手術を受けることになったのでした。
2回目の大腸内視鏡は、1回目よりも大変でした。というのは、今回は腸を切っているので、粘膜が回復するまで、食事制限が継続したからです。
術後1週間、油ものはだめ、野菜はだめ、パンなどの消化の良いものしか食べられない。
自分で作る朝食と夕食は食べられるものだけを使って作ればよいですが、昼食が面倒でした。コンビニやスーパーのお弁当はたいてい揚げ物ですし、付け合わせの野菜もついていますし、選べるものがあんまりない。しかたがないのでプレーンな食パンやらおにぎりやらを食べるのですが、あまりにも味気ない。途中からはカロリーメイトを食べればいいという気づきを得て昼ごはんがかろうじて「味」を取り戻すのですが、切なさの募る日々を過ごすことになりました。
1週間が経って血便が出なくなり、おそるおそるオイルパスタを食べて、何事もなかったときの解放感はひとしおでした。
このときのことは、その後、なんとなく昼食メニューのひとつになったカロリーメイトを食べていたら、居合わせた上役から「院長がお昼にそんなものを食べていたら、実習生からろくに昼食もとれない病院だと思われるからやめなさい」と理不尽に叱られたことも含めて、なかなかにしんどい体験として記憶されています。
それでも、まあ振り返ってみれば、健康診断で潜血反応が見つかって、きちんと治療にまでつながったことは幸いだったと思います。医者の不養生といいますか、自分自身の健康状態にあまり興味のない人間なので、健診を受けていなければ、ポリープの存在にも気づかずずっと放置していたはずですから。
健康診断、大事です。
健康診断の意義
と、いうわけで、今回は、動物も健康診断が大事だよ、という話をしていこうかと思います。病院に来るだけでもストレスを感じる動物たちを、トラブルがないのにわざわざ病院に連れてくることに抵抗のある飼い主さんも少なくないでしょうが、それでも連れてくるだけの価値が、健康診断にはあるからです。
動物に定期検診を受けさせる意義は、3つあります。順番にみていきましょう。
病気の早期発見
ひとつめは、隠れた病気の早期発見につながること。
気づかぬうちに私が大腸ポリープを抱えていたように、動物も、知らず知らずのうちに病気を抱えてしまっていたということはよくあります。かつて、猫の肥大型心筋症という病気は、突然死を招く病気でした。重篤になるまでほとんど症状が現れないため、気づかれないまま進行してしまっていたからです。いまでは、心臓の検査によって早期に発見し、進行を抑えることができるようになっていますが、症状が現れないまま進行する点は変わらないため、定期的な検査を受けなければ、やはり手遅れの状態で病気に気が付くということになってしまいます。
当グループのデータでは、健診を受けた犬猫の27%に病気や異常が見つかっています。7歳以上に絞ると、そのパーセンテージは犬で40%、猫で32%に上がります。なかなかの確率ですよね。隠れた病気を早期に見つけるために、健康に見えても健診を受けるのはとても大事なことなんです。
基準値の把握
ふたつめは、その子にとっての基準値を把握できること。
血液検査などを受けると、各項目の結果が「基準値」とともに伝えられ、基準に比べてどれくらい高い(あるいは低い)からこういう病気が疑われる、といった説明をされるかと思います。ここで用いる「基準値」は、ざっくり言えば、たくさんの健康な動物を集めて数値を調べ、「だいたい」この範囲におさまるからこれを基準値にしよう、ということで決めているものです。
「だいたい」ということは、裏を返せば、すべての動物がその基準値の中におさまるというわけではないということです。健康であっても、基準値から外れた数値を示す動物は存在します。
そのような動物が体調を崩して検査したとき、その子の健常時の数値がわからなければ、基準から外れた数値が病気によるものなのか、もとからのものなのか判断がつきません。そのために、原因を見誤ったり、余計な治療をしてしまうリスクが出てきます。
まめに健診を行い、健常時の数値を把握しておくことで、このようなリスクを小さくすることができるのです。
通院への馴致
みっつめは、動物が病院に慣れやすくなること。
これは、健診以外での予防目的の受診や、受診後のご褒美といったものと組み合わせることで得られる効果ですが、健診を含むさまざまな理由で動物をまめに病院に連れてくることで、動物自体がだんだん通院に慣れてきます。これによって、いざ動物が病気になって、入院しなければいけなくなったようなときに、そのストレスを小さくしてあげることができるのです。動物が、入院中ずっと緊張しているのと、リラックスしているのとでは、治療の受けやすさも、回復までの速さも違ってきます。
これらの意義があることから、当院では、定期健診の受診を推奨しています。
健康診断の頻度
では、いったいどれくらいの頻度で、動物に健診を受けさせてあげればいいのでしょうか。
人間の場合、労働基準法では、労働者に最低年1回の健診を受けさせることが事業者に義務付けられています。学校保健安全法でも、児童生徒に年1回健康診断を受けさせることが定められています。どうやら、年1回というのが、人間におけるスタンダードな健診頻度のようです。ならば動物も、それ相当の頻度で健康診断を受けることが望ましいのではないかと思われます。
注意しなければならないのは、伴侶動物のほとんどは、人間より早く歳を取るということです。その分病気の進行も早いとすれば、人間における「1年ごと」に相当するスパンは、動物ではもっと短くなるでしょう。
たとえば犬や猫は、1年で人間の4年分歳を取ると言われています。この数字自体は単純な比例計算なので、生理学的にほんとうに4倍のはやさで歳をとっているかどうかはわかりませんが、少なくとも年1回の健診では間隔が長すぎることは伺えます。
そこで、当グループでは、最低年2回の健診を受けることをお勧めしています。
健康診断を受けるときの注意点
最後に、健康診断を受けるときの注意点について書いてみます。
ひとつめは、人間と同じで、絶食状態で検査を受けること。食べ物を食べた後だと、超音波検査をしたときに胃が膨れてほかの内臓が見えなくなってしまったり、血液検査の数値に影響が出たりします。さまざまな基準値は空腹時のデータをもとに決められているので、検査を受ける際も同じ条件で受けていただいた方が正確な判断ができます。
ふたつめは、普段の動物の状態をよく見ておくこと。おうちでの様子について質問する「問診」も、血液検査やレントゲン検査と同じように重要な「検査」です。検査でグレーな結果が出たとき、経過観察とするのか治療介入をするのかを判断するには、動物の様子が大事な判断材料になります。すべて病院任せでなく、飼い主さんご自身が動物の健康状態に日頃から気を配っていただくことで、健診の効果はより高くなるのです。
みっつめは、なるべく落ち着いた状態で、動物を連れてきていただくこと。興奮や緊張も、検査の結果に影響を与えることがあります。来院のストレスをゼロにすることはできませんが、臆病な子であれば周りが見えないようにしてきてもらう、自家用車やタクシーを利用してなるべく外部からの刺激を少なくしてもらうといった工夫をしていただくことで、正確に、スムーズに健診を進めることができるようになります。
キャリーの様式も重要なポイントです。たとえば猫は、正面から引きずり出されるのを非常に嫌がる一方で、上から持ち上げられることはそんなに嫌がりませんから、上部に扉がついているタイプのキャリーでお連れいただくと、ストレスを少なくして検査を進めることができます。
これらのことに気を配っていただくと、健診の効果を最大限受けられるでしょう。
最後に
医療ドラマでは、深刻な病気にかかった患者を天才的な腕でブリリアントに助ける医者がヒーローになりがちです。現実の医療を扱ったドキュメンタリーでも、スポットが当たるのはヒキの強いそういう場面ばかり。それらが印象的なものですから、「医療とはそういうものだ」と私たちはつい考えてしまいます。
でも、本当はそうじゃないと、私は考えています。
野球でも言うじゃないですか。「打球が放たれてから走り出して、スライディングしてキャッチする、いわゆるファインプレーをする選手は実は二流。一流の選手は打球の落ちる場所を予測して、はじめからそこに立っている」と。
どうぶつの医療もそれと同じ。重症のどうぶつを助けることももちろん大事ですが、それ以上に、「どうぶつを病気にさせない、軽症のうちに治す」ことのほうが重要だと思っています。どうぶつが辛くなってから手を打つより、辛くならないようにしてあげるほうが絶対いいですよね。
ただし、そのためには、飼い主のみなさんの協力が必要です。我々は、動物病院に来ないどうぶつを助けてあげることはできません。どうぶつの健康を守るためには、飼い主のみなさんが、どうぶつを病院に連れてきてくれなければならない。
だから、みなさんにはぜひ、大切な家族に、積極的に健診を受けさせてあげて欲しいと思います。
ちなみに大腸ポリープの手術を受けた私は、最後にお医者さんから、ついでのように「あとここに痔のエケチェンがいるから(意訳)」と言われました。おかげで肛門の血行に気をつかう日々を送ることができ、エケチェンが反抗期に入るのを防ぐことができています。これも健診を受けていたおかげですね。
健診、大事です。
アーカイブ
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (7)
- 2025年12月 (10)
- 2025年11月 (8)
- 2025年10月 (4)
- 2025年8月 (1)
- 2025年6月 (2)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (6)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (4)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (5)
- 2022年11月 (4)
- 2021年11月 (1)
- 2021年9月 (1)
- 2021年3月 (4)