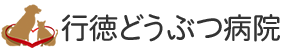ブログ
適切な給餌量について
2025.05.15
院長ブログ
はじめに
こんにちは。行徳どうぶつ病院、院長の名古です。
当院にかかられている方はご存知でしょうが、私、かなり痩せ型の体型をしています。先日の健康診断時の身体測定では、BMIが16.1でした(体重を書くと、前回の記事との合わせ技で妻の体重がばれてしまうので、ぼやかしますすみません)。お付き合いさせていただいた女性が軒並み、自分の体重を目標にダイエットをはじめるという経験をしてきています。喧嘩を売っているわけではありません。
だからといって、食が細いかというとそうでもない。一度に食べる量はそれほどでもないですが、休日など、わりと絶え間なくお菓子を食べ続けていたりして、総摂取エネルギーはかなりのものになっていると思います。それでも太らない、というか太れない。タニタの機器が判定した基礎代謝レベルは高い方に振り切れていて(なのに冷え性なのが解せない)、まあかなり燃費の悪い身体をしているようです。食べたものが全然身にならないということですね。喧嘩を売っているわけではありません。
この体質はおそらく母から受け継いだものですが、当の母はといえば、50歳を過ぎてから明らかに太りやすくなりました。これは年齢による代謝の変化もあれば、患っている病気の影響もあるでしょう。昔は私と同じように間食の多かった母ですが、今は摂取エネルギーを気にしながら生活しています。
何が言いたいのかというと、どのくらいのエネルギーを取ればいいのか、すなわちどれくらいの食事を食べればいいのかというのは、体質や年齢や病気の有無などさまざまな要素がからむ問題で、簡単に何キロカロリー取ればよいと算出できるものではない、ということです。
もちろん動物も同じ。目安、平均値的なものは存在しますが、目の前の動物が、いま、どれだけのエネルギーを必要としているかを正確に知るのは至難の業です。
では、飼っている動物への給餌量は、どうやって決めたらいいのか。
今回は、そのお話をしてみようと思います。
体重・BCSがバロメーター
適切な給餌量をみつけるためのヒントは、前回投稿した記事のうちにあります。
そう、体重を測ればいいんですね。
給餌量が適切ならば、成長期には少しずつ体重が増えていくでしょう。成長期を過ぎてからは同じくらいの体重を維持していくでしょう。体重が減ってしまうならば給餌量が少ないということですから増やさなければいけませんし、成長期を過ぎているのに体重が増えてしまうとしたら給餌量が多いということになりますから、給餌量を減らさなくてはいけません。
体脂肪のつき具合を示すボディ・コンディション・スコア(BCS)も重要な指標になります。成長期、体重が増えていても、それが身体の(骨格の)成長に追いついていない場合は、BCSが下がってきます。その場合は、適正なBCSになるように、給餌量を増やさなくてはいけません。成長期を過ぎていても、保護猫など、栄養状態が悪い動物をお迎えした場合は、BCSが適正になるレベルまで体重が増えるように、しっかり食べさせてあげる必要があります。
このように、体重・BCSの「変化」をみて、それに合わせて給餌量を増減していけば、その子にとってベストな量をみつけてあげることができるのです。
はじめの量はどうする?
とはいえ、飼育を開始する時点では、なんらかの目安をもとに、はじめの給餌量を決めてあげなくてはいけません。それは、どのようにして決めればいいのでしょうか。
犬や猫のように、フードが充実していて、給餌量の目安がフードのパッケージに書いてあるような動物ならば話は簡単。その表記を目安にしましょう。伴侶動物として歴史の長い動物は、この点が楽ですね。あくまで目安なので、その数字に囚われすぎてはいけませんが。
問題は、そういった目安のとくにない動物です。ウサギやフェレットなど、家畜化された種を除くほとんどのエキゾチックアニマルは、どれくらい給餌したらいいのか、基準がきちんとわかっているわけではありません。
こういった動物を飼育する場合、私はひとまず、満腹になるまで食べさせてみることにしています。いまうちにいるニシアフリカトカゲモドキを飼い始めたときも、とりあえず食べるだけ与えてみて、どれくらいで「もういらない」となるかみていました。そのようにして満腹になる量がわかったら、次からはその8割程度の量(腹八分目ですね)を与えるようにします。その後、数日おきに体重を測って、調節していきます。このやり方で、たいていはいい感じの給餌量を掴むことができます。
犬や猫でも、保護したての子でひどく痩せている場合は、慣れていないとフードの給餌量目安もどこを見ればいいかわからなくなってしまうので、「とりあえず満腹にさせる」サンジ方式から入ってみるとよいでしょう。「さァ食え!! 食いてェ奴にゃ食わせてやる!!」なんて言いながらね。
余談
ちなみに、主観的なものになるので余談として聞いていただければと思うのですが、飼っているニシアフリカトカゲモドキにコオロギを給餌するとき、私は彼の「顔色」で判断していたりします。飼っていると、だんだんわかってくるようになるんですよね。「こいつ、あと1匹食べたら満腹っぽい」みたいなことが。なので、その1匹を与えずに給餌を終えます。これはなにも私の特殊能力ではなくて、とくに長年エキゾチックアニマルを飼っている方は一般的に備えている感覚だと思います。才能というよりは、修練の先に得る力。野性。その域まで達しているなら、もはや私の出る幕はありません。
けれど、その感覚を掴めるようになるまでにはそれなりに時間がかかります。慣れてくるまでは、ここで述べたような方法をとってみることをおすすめします。
さいごに
以上、飼育動物の適正な給餌量について書いてみました。
大事なことは、教科書的な「標準」にとらわれることなく、目の前のその子をしっかりと見てあげることです。その子の変化を細やかに捉え、フィードバックしていく感覚が掴めれば、少なくとも給餌量で悩むことはなくなるでしょう。
考えてみれば、やっていることは人間がダイエットをするときと同じなんですよね。体重をこまめに測って、それに合わせて摂取エネルギーを調整していく。体重管理の基本のキ。それを動物たちにもやってあげましょう、というだけの話ではあります。なので、これを実践することで、つられて人間の方のダイエットもうまくまわり始めるかもしれません。動物のお世話をきっかけに、飼い主も健康になる。そういう流れが作れたら理想的ですね。
と言いつつ、白状するとこの文章を書いているあいだに、気が付いたら私はポテチの大袋(150g弱くらいあるやつ)を一袋完食してしまっていたんですが。もう40になるのに、底辺の食生活。それでも健康診断で異常がなく、内臓年齢16歳と判定されるような体質に生んでくれた母に感謝する毎日です。
喧嘩を売っているわけではありません。
アーカイブ
- 2026年2月 (3)
- 2026年1月 (7)
- 2025年12月 (10)
- 2025年11月 (8)
- 2025年10月 (4)
- 2025年8月 (1)
- 2025年6月 (2)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (6)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (4)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (5)
- 2022年11月 (4)
- 2021年11月 (1)
- 2021年9月 (1)
- 2021年3月 (4)