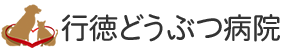整形外科
膝蓋骨脱臼について
概要
大腿骨下の溝にはまっている膝蓋骨(膝のお皿)が正常な位置から外れてしまう病気です。膝の内側に外れる「内方脱臼」と、外側に外れる「外方脱臼」があり、小型犬では内方脱臼がよくみられます。
原因
膝蓋骨脱臼は先天性と後天性に分類されます。先天性のものは、膝関節周囲の靱帯が生まれつき緩い、大腿骨に形成異常があるといった原因で発症します。後天性のものは、転落、交通事故などによる衝撃が原因で起こります。
治療
症状が軽ければ、保存療法を行います。保存療法とは、鎮痛薬やサプリメントなどを使い、脱臼による痛みを緩和する治療法です。一方、後述の前十字靭帯の断裂などを伴い、痛みや歩行障害が強くなるようであれば、外科療法を行います。手術で大腿骨下方の滑車溝を形成し、さらに大腿の筋肉群〜膝蓋骨〜膝蓋靱帯の軸を再構築することで、膝蓋骨が外れないように整復します。膝に負担をかけないよう筋肉量を維持するためには、水泳などの運動も効果的です。
股関節形成不全について
概要
股関節形成不全(股異形成)は、骨盤と大腿骨をつなぐ股関節が正常に形成されず、関節に炎症を起こしたり、股関節脱臼を起こしたりする疾患です。一見して症状がほとんどない場合もあるため、発見が遅れてしまう可能性があります。早期発見・治療を行うためには、子犬を飼い始めたときからこまめに健康診断を受けることが大切です。
診断
症状、触診、レントゲン撮影などを行い診断します。成長期では、まず触診にて股関節の痛み、関節の緩みなどのチェックを行います。重度の場合、触ったときに捻髪音(パリパリという細かな音)や股関節可動域の減少が見られます。腰を振るような特徴的な歩き方もこの疾患を疑う症状です。触診の結果、股関節形成不全が疑われた場合は、レントゲン撮影を行います。レントゲンでは、大腿骨を受け止める骨盤の窪みが通常よりも浅いなどの特徴がみられます。
治療
状態が軽度で痛みもないならば、体重管理や運動制限などの環境改善を行います。炎症・疼痛を伴う場合は、鎮痛薬の投与によりそれらを和らげます。脱臼を繰り返す、炎症が強く鎮痛薬をやめられないといった場合は骨頭切除などの手術を行います。
前十字靱帯断裂について
概要
前十字靱帯とは、大腿骨と脛骨をつなぐ靱帯のことです。 主な機能としては脛骨が前方に出すぎないように抑制すること、膝の関節の過伸展を抑制することなどが挙げられます。この靭帯が断裂・損傷して膝の関節が不安定となり、痛みや、半月板などの周辺組織が損傷する疾患を前十字靭帯断裂とよびます。ゆっくりと靭帯の変性が進行することで起きる慢性断裂と、急激に大きな負荷が靭帯にかかることによって起きる急性断裂に分けられます。犬の前十字靭帯断裂は、ほとんどが慢性です。
原因
急性断裂は、激しい運動や事故などによって発生します。慢性断裂は、遺伝的・免疫学的・形態学的な要因、加齢による靭帯の変性などによって発生します。小型犬では前述の膝蓋骨脱臼に伴って発生することが多いです。
症状
膝関節が不安定になり体重が支えられなくなるため、跛行(歩き方の異常)が生じます。慢性の断裂では、一時的に跛行が生じても歩行機能を取り戻すことがありますが、何度かその状態を繰り返すことで変性性関節疾患や半月板損傷、関節炎が発生し、次第に進行・悪化していきます。
治療
軽症の場合は保存療法を行うこともありますが、機能回復のためには手術が必要となります。従来は縫合糸などで靭帯の代わりに骨をつなぐ方法がとられていましたが、現在は特殊なインプラントによって関節を再構築する機能安定化術という方法が主流となっています。当院の整形外科外来でも後者の方法で治療を行なっています。椎間板ヘルニアについて
概要
椎体と椎体の間にある椎間板が変性し、その内容物(髄核)が脊柱管内に突出し脊髄が圧迫されることで、神経障害を引き起こす病気です。
症状
ヘルニアの発生した部位やヘルニアの程度によって、疼痛、破行、麻痺などさまざまな症状があらわれます。 重度の頚部椎間板ヘルニアでは、突然呼吸停止を引き起こすこともあります。
診断
レントゲン検査でわかることもありますが、後述の手術のために詳しく状態を把握するにはMRIが必要になります。治療
軽度の場合は、鎮痛薬の投与、安静などの保存療法を行うこともあります。麻痺が生じるような重症例では、手術を行い、圧迫部位を取り除きます。
変形性脊椎症について
概要
脊椎の椎体自体が変形し、脊髄を圧迫することで神経障害を引き起こす病気です。一般的には老化が原因で発症しますが、過度の運動や外傷、栄養不足などによっても発症することがあります。また、生まれつき椎体が変形しているケースもあります。
症状
腰痛、歩行異常、神経障害などです。痛みのある部位を繰り返し舐めることで脱毛が生じることもあります。痛みによりつよくいきむことができず、便秘につながる場合もあります。
治療
鎮痛薬やサプリメントの投与などを行います。